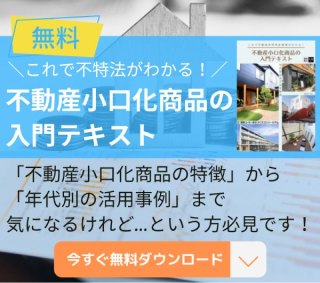相続できない?!厳格化された「小規模宅地等の特例」の注意点とこれからの相続対策

相続対策は、相続が発生する前から準備することが理想です。建物が立っている場合も含め、土地の相続がある場合は、「小規模宅地特例」を利用して、相続税の節税対策が可能です。
小規模宅地等の特例は節税効果が大きいことから、特例の適用を受けるべく、様々な方法が考えられてきました。
しかし、不自然な資産の取引により、形式的に「小規模宅地等の特例」適用の要件を整え、この制度を悪用する例もあり、問題になっていました。
それにより、小規模宅地特例は平成30年に制度が厳格化され、相続税の節税対策ができないケースもあります。
いざという時に困らないよう、「小規模宅地特例」の注意点を理解しておきましょう。
小規模宅地等の特例とは?
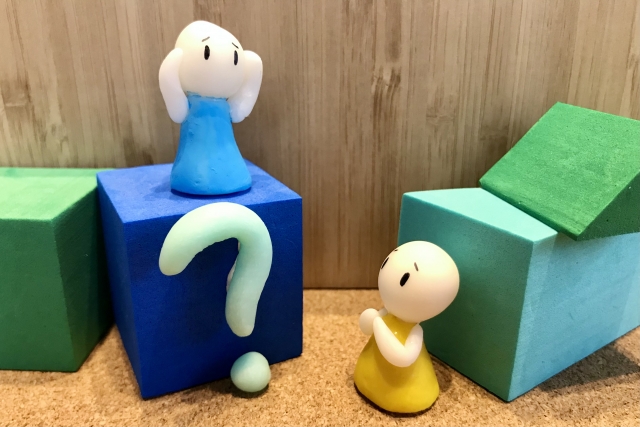
小規模宅地等の特例とは、亡くなった方の自宅を相続する際、一定要件を満たせば「小規模宅地等の特例」が適用でき、自宅敷地の330㎡までの部分について、相続税評価額が80%減額される相続税法上の特例制度です。
小規模宅地等の特例が適用できれば、自宅敷地の相続税評価額が80%減額されることから、節税対策として利用する方法が考えられてきました。
2018年4月7日付日本経済新聞によると、2015年分で小規模宅地等の特例の適用件数は67,325件(相続税の申告件数全体の5割相当)、減額された金額は1兆354億円にもなります。
ところが、平成30年の税制改正により、相続税における「小規模宅地等の特例」が改正されました。
その内容は、持ち家に居住していない相続人、いわゆる「家なき子」が小規模宅地等の特例を適用するための要件が厳格化されたのです。
持ち家に住んでいない相続人を優遇する特例を悪用?し、行き過ぎた節税に網をかけるべく、改正されたとも言えます。
この改正により、相続税対策として行っていた方法が節税対策にならず、都心の一等地など、相続税評価の高い地域に自宅を所有している方は、大きく相続税が増える可能性もあります。
よって、小規模宅地等の特例を活かした節税対策を見込んでいる方いた方は、別の方法を考える必要があります。
小規模宅地等の特例の対象となる土地(宅地)は3種類に分けられる
「小規模宅地特例」とは、土地の相続税減税に関する特例です。大きく分けて、以下の3種類に分けられます。
①特定居住用宅地等
②貸付事業用宅地等
③特定事業用宅地等
特定事業用宅地とは、亡くなった人の個人事業に使用されていた土地のことですが、アパートや駐車場などで使用している土地に関しては、貸付事業用宅地に含まれます。
亡くなった方の自宅を相続する特定居住用宅地のケース、アパート経営をしていた土地を相続する貸付事業用宅地に適応されるケースについて、詳しく解説していきます。
亡くなった方の自宅(宅地)を相続するケース|家なき子(特定居住用地)の事例
小規模宅地等の特例とは、亡くなった方の親族が、その家に住み続けられるように配慮されたものです。相続税を納税するために、家を売らなければならない事態を避ける目的として設けられている特例と言えます。
原則、亡くなった方と同居していた親族が相続する場合に適用できます。
しかし、仕事の都合による転勤など、やむを得ない事情から同居できないケースも考えられます。
そのため、持ち家に居住していない親族(家なき子)が、亡くなった方の自宅を相続した場合についても、次のような要件により、特例を認めています。
- 被相続人に配偶者や同居の親族(相続人)がいない。
- 被相続人の自宅を相続する人は、相続前の3年以内に自身または自身の配偶者が所有する家屋に居住したことがない。
- 亡くなった方(被相続人)の自宅を相続する人は、相続した宅地を相続税の申告期限まで保有する。
これが「家なき子の特例」と呼ばれているものです。
このうち、「相続前の3年以内に持ち家に住んだことがない」という要件について、「相続人に持ち家があっても、相続までの3年間は持ち家でなければ良い」という解釈をもとに、節税対策として活用されていたのです。
例えば、
- 自分の持ち家を妻や子などの親族に贈与することで、自分は持ち家を所有していない形態にする。
- 自分の資産管理法人を設立し、その法人に持ち家を売却して賃貸住宅に暮らしている形式にする。
など、作為的に持ち家がない状態(家なき子)にする節税対策が行われるようになり、実質的に自宅を所有していても、相続があったときには「家なき子の特例」が適用できたのです。
平成30年改正|節税目的で作為的な「家なき子」は認められない
本来、「家なき子」の特例は、持ち家のない相続人が亡くなった方の自宅を相続し、その自宅に移り住むことを想定した特例と言えます。
平成30年の税制改正により、次のようなケースは小規模宅地等の特例が適用できなくなりました。
- 相続の前の3年以内の期間に、3親等以内の親族またはその親族と特別の関係のある法人が所有する家屋に居住したことがある場合。
- 相続人が相続開始のときに居住していた住宅を過去に所有していたことがある場合。
※この改正は、平成30年4月1日以降に相続または遺贈が行われた場合について適用されます。
つまり、これまでに行われていた形式的に家を持っていない状況をつくり、作為的に「家なき子」状態にする節税対策は通用しなくなります。
親に買ってもらった親名義の家に住んでいる人も家なき子ではなくなります。
遺言などで孫に相続させる場合でも、孫が親の持ち家に住んでいれば「3親等以内の親族が所有する家に居住」に該当するため、特例は使えません。
どうすれば「家なき子の特例」が適用できる?
では、家族を自宅に残し、自分だけが親と同居していれば良いのでしょうか?
明確な判断基準があるわけではありませんが、住民票だけ移しても、「実態」が伴わない親との同居は、認められない可能性が考えられます。
自宅敷地について小規模宅地等の特例適用を考えるならば、勤務先が遠方で自宅を購入してしまっているケースは難しいとしても、本当に同居する可能性を検討する方が現実的と言えます。
自宅の評価を活用した資産形成による節税対策
親の自宅が都内の一等地など、相続税評価の高い立地の場合、小規模宅地等の特例を使わなければ、相続税の納税額が数千万円単位で税額が増える可能性があります。
納税資金が準備できなければ、相続税納税のため家を売却しなければなりません。
一方で、相続税評価の高い自宅敷地であれば資産価値の高い不動産と言えます。
この資産価値を活用し、不動産投資などによる節税対策を考えることが可能です。
資産価値が高ければ、金融機関の担保評価も高くなるため、融資を受ける際には有利となります。
資産価値の高い不動産を手放して納税するか?
資産価値の高い不動産を活用し、収益性のある不動産を手に入れると同時に、相続税の節税効果を手に入れるか?
親が残してくれる自宅は価値の高い不動産なので、何も検討せずに売却して納税するだけでは、もったいないと言えます。
せっかく資産価値の高い不動産があるのですから、将来を見据えた資産形成を含め、不動産投資による節税対策の検討も、一考に値するのではないでしょうか?
アパート経営の土地を相続するケース|貸付事業用宅地等の事例
貸付事業用地等の小規模宅地等の特例という仕組みがあり、アパートやマンションなどの賃貸住宅の敷地のうち、200㎡までの部分について相続税評価額を50%減額することができます。
この特例を活用し、相続税対策として相続発生直前に金融資産などを不動産に換えることで、評価の差額を活用した節税対策が行われてきました。
土地評価額の高い物件ほど効果が大きくなるため、不動産価格が上昇している背景もあり、盛んに行われていた節税対策とも言えます。
例えば、
- マンションなどを現金で購入して賃貸として貸す
- 相続時には購入価格の20~30%程度の相続税評価額で申告し、相続税の納税額を抑える
- 申告後、すぐに購入価格よりも高い金額で売却し、現金を手にする
などの手法です。
ところが、平成30年の税制改正で、貸付事業用宅地等における小規模宅地等の特例の適用基準が厳しくなり、相続開始前3年以内に賃貸を始めた宅地が除外されることになりました。
このような行き過ぎた節税対策が多く行われたため、規制されたと言えます。
では、相続直前に不動産投資を行っていた場合は、相続税の節税効果はないのかというと、貸付事業用地等における小規模宅地等の特例が適用できないだけで、相続税の節税効果はあります。
但し、注意すべきポイントがありますので、注意点を把握しておきましょう。
3年以上前から事業的規模で賃貸していれば引き続き特例の対象
相続開始の3年以上前から事業的規模で賃貸を行っている方は、3年以内に賃貸を始めた物件があったとしても、小規模宅地等の特例が適用されます。
この事業的規模については、明確にはなっていませんが、所得税の基準(5棟10室)が目安になるのでは?言われています。
つまり、戸建てなどの貸家は5棟、共同住宅であれば10室以上の賃貸住宅を3年以上前から経営していることが事業的規模に該当すると推測されます。
相続直前の不動産投資も節税対策になる
平成30年の改正により、「相続直前の不動産投資は、全て相続税対策にならない」と思われている方もいますが、実際は相続直前の不動産投資でも節税効果があります。
以前にあった「相続開始前3年以内に取得した不動産の評価は、取得価格(時価)で評価」される時代があったため、勘違いしやすいのかもしれません。
貸付事業用地等における小規模宅地等の特例適用ができないだけで、実際は取得価格(時価)と相続税の評価基準で試算される相続税評価額の差を利用した節税対策は今でも有効です。
つまり、相続直前に行う不動産投資でも、相続税対策は効果があるのです。
但し、明らかに節税目的だけの不自然な不動産投資では否認されるケースも考えられるため、間際になって慌てて節税対策を行うのではなく、事前に準備しておくことが大切です。
節税効果を手に入れるまでの時間を考えること
不動産投資は、相続税の節税対策として有効ですが、人の不幸はいつ訪れるかわかりません。
事前にしっかりと準備しておくことが大切です。
例えば、土地の有効活用では、相続税対策を考えてから節税効果を得るためには時間がかかります。
建物をつくるまでの時間が必要だからです。
設計や工事の期間を考えると、木造アパートの場合は約1年、鉄筋コンクリートのマンションの場合は1年半から2年は必要です。さらに、検討期間も加味すれば、それ以上の期間が必要になります。
仮に、工事期間中に相続が発生した場合、大きな節税効果は望めません。
一方で、不動産投資により完成物件を取得する場合、取得した時点で節税効果も手に入れることができます。
ご高齢のため、時間的余裕がない場合には、土地を所有していたとしても、不動産投資による完成物件を購入する方が良いケースがあります。
相続発生後すぐの売却には注意
不動産投資により取得したアパート・マンションを、相続発生後すぐに売却することは注意が必要です。
例えば、Aさんは相続発生の1ヶ月前に、相続税の節税対策として、1億円で都内の不動産を現金で購入しました。
この不動産の相続税評価額(建物:固定資産税評価額、土地:路線価)を基準に算出すると、約3,000万円(購入価格の約30%相当)でした。
Aさんより不動産を相続したBさんは、その相続税評価額(3,000万円)で相続税の申告をしました。
Bさんは、相続税の申告後(相続発生の翌年)、購入価格とほぼ同額の1億円で売却しました。
つまり、現金1億円で不動産を購入し、3,000万円の評価額として相続税を計算して申告・納税したにも関わらず、実際には1億円の現金を手にすることができたのです。
このようなケースは税務署が否認し、「相続税評価額は購入価格」とされる可能性があります。
相続税評価額と市場価額の差が大きい物件で、相続後すぐに売却するようなケースは「行き過ぎた節税対策」とみなされる場合があり、相続税評価額は市場価額に修正し、追徴課税される可能性があります。
他に売却する資産がなく、この物件を売却しなければ納税できないようなケースでは認められる可能性もありますが、どのようなケースが「行き過ぎ」とみなされるか判断基準が明らかにされてはいませんので、節税目的だけの方法には注意が必要です。
まとめ
小規模宅地等の特例をご紹介してきました。
小規模宅地等の特例が適用できない場合には、別の節税対策を考える必要があります。
その一つとして、不動産投資による節税対策が考えられます。
相続税の納税額が大きくなるという事は、親の自宅は資産価値が高い不動産と言えます。
価値の高い不動産があるのですから、不動産投資などによる節税対策を検討することにより、資産形成をしながら節税対策が図れることになります。
尚、税制改正に関する小規模宅地等の特例について、詳しくは相続税などに詳しい税理士に確認・ご相談することをお勧めします。
そして、自宅ではなく所有アパートの相続に対しても、駆け込みでの貸付事業用宅地等における小規模宅地等の特例が適用できません。
しかし、所有アパート相続の場合、この特例が適用できないだけで、取得価格(時価)と相続税の評価基準で試算される相続税評価額の差を利用した節税対策は有効です。
しかし、相続直前に不動産投資を行い節税し、相続後すぐに売却してしまうような、単に節税目的だけの不動産投資は否認されるケースもあります。
もともと不動産投資には節税効果がありますが、安定収益を確保するために、しっかりと賃貸事業を担うことが重要です。
不動産投資には少なからずリスクがありますので、節税目的だけでは本末転倒な結果となる場合があります。
事前にしっかりと検討した上で、節税対策を手に入れつつ、次世代へ資産を受け継ぐという中長期の視点により、賃貸事業として考えることが一番のポイントです。
深く検討せず、親の残してくれた資産を簡単に手放してしまうのではなく、その資産価値を活用することで、親から引き継いだ資産を守り、親から子へ、子から孫へと、将来を見据えた資産形成を視野に、今ある財産の在り方を検討してみてはいかがでしょうか。